|
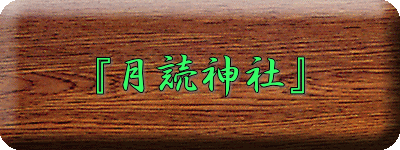
野田 英世
毎回郷土の紹介をしていますが、今回もその一つ「月読神社」についてご紹介します。以前にもお話しましたが、
私の住んでいる京都洛西の地「桂」は昔(1400年ほど前)渡来人の「秦氏」によって開拓された土地です。した
がって至る所にその面影を残す遺跡があちらこちらに残っています。
伝説によると、神代の代に天から降臨してきた「月読尊」(つきよみのみこと)が降り立ったところが桂川の畔で
、そこに大きな桂の木があったそうです。そのせいか、桂には桂離宮を初めとして月見に関わる史跡が多くあります。
「月読尊」は「古事記」、「日本書紀」の神話で天照大神の弟神とされているが「月神命」とも言われ伝承されて
います。アマテラス大神が太陽信仰なのに対して「月読尊」は月信仰なのです。一方長崎県玄界灘の北方にある壱岐
にも「月読神社」があります。ここは海の干満を司る神とされ、やはり「月神」であり「海神」でもあるギリシヤ神
話にでてくるネプチューンみたいな神でしょうね。文献によると、朝廷の使者「安倍臣事代」(あべのおみことしろ
)が任那(みまな)の国(朝鮮)の帰りに壱岐に寄り、ここの月読神社にお参りし当時の都の飢饉救済を願ったとこ
ろ、京にも月読神社を建てよとのお告げがあり、それに基づいて建てたそうです、だから壱岐の月読神社は桂の月読
神社の元祖になるわけです。
桂の「月読神社」は5世紀末ごろ(平安京遷都より以前)に建てられたものと有力視されています。近くの「松尾
大社」よりも古くからある神社だそうです。今では松尾大社の勢力に押されて「摂社」つまり支社扱いになっていま
す。新年を迎えて大繁盛する松尾大社に比べその南300m程にある月読神社はひっそり感と静まり返っています。
何時に始まったのか怪しいものですが今では安産の神さんになっています。“月が満ちる”と言いますから、やはり
そこから来たものと思われます。月読神社には「月延石」(安産石とも言われています)というものが祭ってありま
して、神功皇后が応神天皇を生む際にこの石で腹を撫でて安産し後に舒明天皇の時に当社に奉納されたという言われ
が残っています。また応神天皇の誕生に際して産み月を立派な子供をさづかるため3年遅らせたことから月延石とも
言われる由縁とも伝えられている。一方神社の裏に「安産木?」というのがあり、これは何の木か知りませんが古い
大木で女性のシンボルにたとえられる姿をした銘木で必見に値するものです。一度是非訪れてみて下さい。
従って、「月読尊」は天照大神の弟と歴史上はされていますが、どうも妹で女性神ではないかとも推測されます。
ひょっとしたら全く関係がなく後の時代にこじつけたのかも知れません、そう言ってしまうとみもふたもありません
が。歴史というものは古書に書いてあれば信用しがちですが、古い話はえてしてそういうものです。

月読神社

月読神社

松尾神社
|